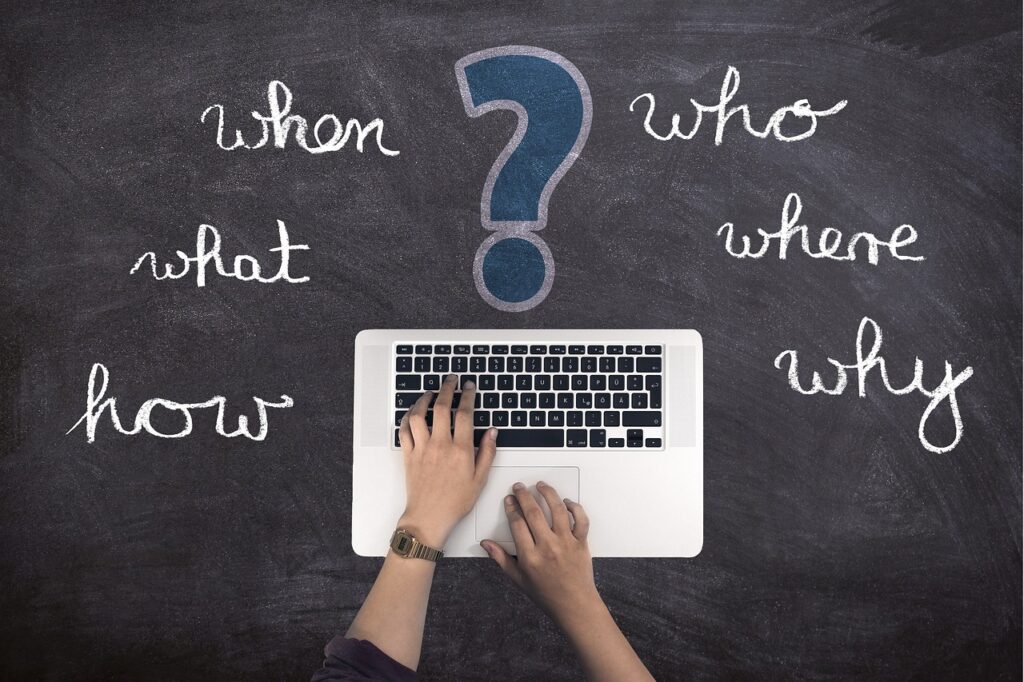ビジネスにおける動画活用の重要性は高まる一方ですが、以下のように悩んでいませんか?
「どの動画制作会社に依頼すればいいのか分からない…」
「選び方を間違えて失敗したくない…」
数多く存在する制作会社の中から、自社に最適なパートナーを見つけるのは簡単ではありません。安易に選んでしまうと、期待外れの結果や、時間・コストの無駄につながるリスクもあります。
そこで本記事では、動画制作会社選びで後悔しないために、押さえるべき重要な14の比較ポイントを解説します。
依頼前の「事前準備編」、複数社を比較する「相見積もり編」、契約直前の「最終選定編」の3つのステップに沿ってまとめました。
YouTubeに関して相談がある方は、StockSun株式会社の鳥屋までお気軽にご連絡ください。これまで120社以上、企業のYouTubeチャンネルを運用した経験をもとに、課題に対してご提案いたします。
\完全無料のオンライン相談会を開催中/
YouTubeに関して相談する目次
動画制作プロジェクトの成否は、どの制作会社を選ぶかに大きく左右されます。なぜ、慎重な会社選びがそれほど重要なのでしょうか?主な理由を3つご紹介します。
まず理解しておきたいのは、一口に動画制作会社といっても、その専門性は多岐にわたる点です。例えば、テレビCMのような大規模な映像制作を得意とする会社もあれば、YouTube動画やSNS広告などWebマーケティングに特化した会社もあります。
作りたい動画の種類や扱う内容の専門性に合わせて、その分野に精通した会社を選ぶことが、質の高い動画制作への第一歩です。
特に、動画を単なる映像作品としてではなく、売上向上や問い合わせ増加といったビジネス成果につなげたい場合は、話しは別です。制作スキルに加えて、マーケティング戦略まで提案できる会社を見つけることをおすすめします。
もし、自社に合わない動画制作会社を選んでしまった場合、貴重なリソースである時間とコストを浪費してしまうリスクがあります。例えば、完成した動画のクオリティが期待に満たなかったり、当初のイメージと大きくかけ離れていたりすると、避けられないのが修正作業です。
特に深刻なのは、時間とコストを注ぎ込んで完成した動画が、本来達成すべき目的を果たせないことです。結果的にかけた予算が全くの無駄になってしまい、得られたはずのビジネスチャンスを逃すことにもつながります。
また、制作会社とのコミュニケーションが円滑に進まず、認識のズレが生じると、手戻りが増えてしまいます。
プロジェクトが遅延する原因にもなるため、注意してください。
動画制作会社を「なんとなく」や「とりあえず」で選んでしまうと、さまざまなミスマッチが発生しやすくなります。
最もよくあるのが、自社の目的やターゲット層と、制作会社から出てくる提案内容や得意な作風が噛み合わないケースです。
集客目的にYouTube動画をつくりたいのに、映像美に特化している会社に依頼すると、目標が達成されない場合があります。
せっかくの動画もターゲットに響かず、目的達成は難しくなります。
もう一つ見過ごせないのが、担当者との相性やコミュニケーションの問題です。動画制作は、依頼主と制作会社が二人三脚で進めるプロジェクトです。
もし、担当者との相性が悪かったり、意思疎通がスムーズにいかなかったりすると、プロジェクト全体がストレスフルになってしまいます。
最適な動画制作会社を見つけるためには、自社の要望や条件を明確にしておくことが重要です。この「事前準備」をしっかり実施することで、制作会社とコミュニケーションしやすくなり、ミスマッチを防止できます。
依頼前に最低限整理しておきたい下記のポイントを見ていきましょう。
最初に「なぜ、この動画を作るのか?」という目的を明確にしましょう。目的は動画制作の出発点であり、プロジェクト全体の方向性を決定づける最も重要な要素です。
目的が曖昧なままでは、制作会社もどのような動画を作るべきか判断できず、効果的な提案も難しくなります。
動画を通じて何を達成したいのかを具体的に言葉にしてみましょう。具体的には下記の通りです。
「新商品の認知度を高めたい」
「Webサイトからの問い合わせを増やしたい」
「採用活動で優秀な人材を集めたい」
目的が明確であれば、動画の構成や盛り込むべきメッセージ、最適な表現方法、そして効果的な配信戦略まで、具体的に検討を進められます。
次に、ターゲット設定です。「できるだけ多くの方に届いてほしい」と考えがちですが、ターゲットを絞り込まなければ、当たり障りのない動画になってしまいます。
理想は、具体的な視聴者像、いわゆるペルソナを設定することです。
例えば、以下のように、年齢や性別、職業、ライフスタイル、興味関心、抱えている悩みなどをイメージしましょう。
「都内在住の30代前半、IT企業勤務の女性で、キャリアアップに関心がある」
「地方の中小企業経営者で、人材不足に悩んでいる」
ターゲットが明確になれば、その人物に響く言葉遣いや表現方法、好まれるデザインテイストなどを選ぶ際に重要です。
また、ターゲットが普段どのような情報に触れているかを考慮し、適切なプラットフォームで動画を配信する必要があります。
しかし、YouTubeチャンネルの目的やターゲットは、どのように選んだらいいか迷いませんか?
このようなコンセプトが決めにくいと思ったら、StockSun株式会社の鳥屋までお気軽にご連絡ください。
これまで120社以上、企業のYouTubeチャンネルを運用した経験をもとに、最適なご提案をいたします。集客や採用につながるチャンネルづくりが得意です。
\完全無料のオンライン相談会を開催中/
YouTubeに関して相談する制作会社に具体的な相談をする前に「いくらまで費用をかけられるか」という予算の上限や目安を決めることも大切です。
予算は、企画内容の自由度、撮影の規模、編集のクオリティ、CGやアニメーションの利用可否など、制作のあらゆる側面に影響を与えます。「〇〇万円以内」「△△万円〜□□万円程度」といった大まかな範囲で構わないので、予算感を設定しましょう。
もし予算の見当がつかない場合は、Webサイトなどで一般的な動画制作の費用相場を事前に調べておくと参考になります。
例えば、YouTube動画の制作費用については、下記の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
>>YouTubeの動画制作・編集にかかる費用相場を徹底解説!費用を抑えるコツもプロが直伝
動画制作を依頼する上で「いつまでに動画が必要か?」という納期を明確にすることも忘れてはいけません。動画を使用したい特定のイベント開催日や、キャンペーンの開始時期などが決まっている場合は、逆算して納品日を設定しましょう。
ここで重要なのは、余裕を持ったスケジュールを心がけることです。動画制作は、企画立案から構成案の作成、撮影や編集、ナレーションやBGMの挿入、複数回にわたる修正作業など多くの工程がかかります。
一般的には、企画のスタートから最終的な納品まで、短くても1ヶ月半、内容によっては2〜3ヶ月かかる場合もあります。計画通りに進まないこともあるため、無理のないスケジュールを立てましょう。
最後は、完成イメージをつくることです。イメージをできるだけ具体的にしておくことが、制作会社との認識のズレを防ぎ、理想の動画が完成されるようになります。
「かっこいい感じで」「感動的に」といった抽象的な言葉だけでは、受け取る側によって解釈が大きく異なる恐れがあります。
そこで最も効果的なのが、参考になる動画をいくつか見つけておくことです。
具体的な映像があれば、言葉では伝えきれない細かなニュアンスやトーンまで正確に共有できます。YouTubeや企業のWebサイトなどをリサーチし、イメージに近いものをピックアップして、打ち合わせ時に提示しましょう。
また、動画で必ず伝えたい核心的なメッセージや、盛り込みたいキーワードなどを事前に整理します。同時に「こういう表現は避けたい」「企業のブランドカラー以外のこの色は使わないでほしい」といったNG項目があれば、明確に伝えます。
事前準備で自社の要望が固まったら、次は実際に動画制作会社を探し、比較検討するステップです。
ここでは、下記5つのポイントを紹介します。
候補となる動画制作会社をいくつか、リストアップします。
Webサイトで公開されている制作実績や評判を調べたり、知人からの紹介をお願いしたりします。その中から、自社の目的やイメージに合いそうな会社を3社程度に絞り込み、相談と見積もりを依頼するのがおすすめです。
なぜ、3社程度が良いのでしょうか?
1社だけでは、その会社の提案や見積もりが適正なのか、比較対象がないため判断が困難だからです。
3社程度であれば、比較検討に必要な情報量を確保しつつ、対応にかかる手間とのバランスが取りやすいと言えます。下記の記事では、大手のおすすめ映像・動画制作会社を紹介しています。
>>おすすめの大手映像・動画制作会社をランキング形式で紹介|失敗しない選び方も
制作会社の実力やセンスを判断する上で、制作実績は有効な情報源です。
各社のWebサイトで公開されている過去の作品を確認し、動画のクオリティを判断します。動画の映像、音声、編集、デザインといった総合的なクオリティが、自社の期待水準に達しているかチェックしましょう。
技術的な高さだけでなく「丁寧に作られているか」「細部までこだわりが感じられるか」といった視点も大切です。
また、自社が作りたい動画のジャンルや業界での実績が豊富かを確認します。ビジネス系のYouTubeチャンネルを開設した場合は、同様のチャンネル運用実績があるかを見るようにしましょう。
類似案件の経験があるかどうかは、見ておきたい判断材料の一つです。
動画制作は、依頼主と制作会社が密に連携を取りながら進める共同作業です。そのため、担当者との円滑なコミュニケーションはプロジェクトの成否に欠かせません。
最初の問い合わせの段階から、打ち合わせを重ねる中で、コミュニケーションに「違和感」がないか観察しましょう。
具体的には、質問に対して、意図を正確に汲み取り、分かりやすく的確に答えてくれているか、QA(質疑応答)にズレが生じていないかを確認します。もし質問の意図と違う回答が返ってきたり、説明が難解だったりすると、その後のやり取りでも苦労する恐れがあります。
「この会社なら意図をしっかり汲み取って、要望に沿った適切な動画を制作してくれそうだ」という視点で判断することが大切です。
優れた動画制作会社は、依頼主の課題を深く理解し、その解決に貢献するための提案力を持っています。単に、依頼された通りの動画を制作するだけではありません。
打ち合わせや提案を受ける中で、その会社の提案力をしっかりと見極めましょう。
重要なのは、こちらの「目的」や「課題」を本質的に理解した上で、解決するための具体的な企画や構成案を提示してくれるかどうかです。
プロの視点からの意見や改善提案をしてくれる会社は、単なる作業者ではなく、共に課題解決を目指すパートナーとして期待できます。
時には、こちらの想定を超えるような斬新なアイデアや、他社との差別化を図れるような独自の視点を示してくれる場合もあります。
候補となる会社から提示された見積書は、金額だけでなく、その内容を詳細に確認することが大切です。
単に「動画1本〇〇円」といった大まかな見積もりだけでは十分ではありません。なぜなら、制作にかかる時間や工数などによって費用は変動する場合があるからです。
YouTubeの動画編集にかかる費用は、1分あたり〇〇円と算出されることが一般的です。見積もりの内訳が分からないと、他社と比較してどのような違いがあるのか正しく判断できません。
また、撮影時間や修正回数によって別途追加費用が発生するのか、その条件を事前にチェックする必要があります。
見積もり段階でしっかりと確認し、不明な点は必ず質問するようにしましょう。
相見積もりとヒアリングを経て、候補が2〜3社に絞られたら、いよいよ最終的な依頼先を決定する段階です。
契約を結ぶ前に、以下のポイントを改めて最終確認し、後悔のない選択をしましょう。
ここでの判断が、プロジェクトの成否を大きく左右します。
候補として残った数社の提案と見積もりを、もう一度、多角的な視点から冷静に比較検討します。単に提示された金額の安さだけで判断するのではなく、その金額に対してどのようなサービス内容が含まれているかを総合的に評価します。
コストパフォーマンスが最も優れているのは、どの会社かを見極めることが重要です。「安かろう悪かろう」では意味がありませんし、逆に高額でもそれに見合う価値がなければ意味がありません。
この最終評価の段階で、見積もりや提案内容、今後の進め方などについて少しでも疑問や懸念点があれば、決して放置してはいけません。必ず質問し、納得いくまで説明を求めて、すべての不明点を完全に解消してください。
「おそらく大丈夫だろう」といった曖昧な判断をするのでなく、この会社に任せたいと思えるところに選びましょう。
実際にプロジェクトが始まってから、制作体制と担当者の役割について、契約前に再度確認しておくことが賢明です。
これまでの商談担当の営業担当者と、実際にプロジェクトの指揮を執るディレクターや主要な制作スタッフが異なる場合があります。
また、制作期間中のコミュニケーションをどのように進めるかについても、具体的に確認し、認識を合わせましょう。特に、キックオフMTGを開始した後は、週1回の定例ミーティングをすることを推奨します。
定期的な対話を通じて認識のズレを防ぎ、プロジェクトをよりスムーズに進めるためにも有効です。
最終的に依頼する会社が決定したら、いよいよ契約のステップに進みます。
内容を十分に理解しないまま安易に捺印してしまうと、後々予期せぬトラブルに発展しかねません。契約を締結する前に、記載されている内容を隅々まで注意深く確認する必要があります。
例えば、支払いタイミングや契約期間、著作権などについて、具体的に記載されているかを一つひとつチェックしましょう。
口頭での約束は記憶違いや解釈の齟齬が生じやすいため、必ず書面上で明確になっていることが重要です。少しでも意味が分からない箇所や納得できない条項があれば、先方に確認することをおすすめします。
継続的に動画制作を依頼する場合は、制作会社との間で「レギュレーション(制作ルール)」を明確にしておくと効果的です。
毎回同じ品質基準や表現方法を口頭で伝えるのは非効率ですし、担当者が変わると認識のズレが生じるケースも考えられます。
そこで、自社が求める動画の品質や表現のトーン&マナー、遵守すべきルールなどを言語化し、資料としてまとめる必要があります。ルール化しておくポイントは、制作会社の編集者が変わったとしても、常に一定のクオリティを担保しやすくなることです。
また、修正指示を出す際にも、レギュレーションに基づいて具体的に指摘できるため、コミュニケーションが円滑になります。
結果的に、制作の時間短縮とコスト削減にもつながります。
動画制作を外注化する際に、パートナーとなる会社選びは重要です。
なぜなら、会社によって得意分野が異なり、安易な選択は時間やコストの浪費、そして目的とのミスマッチにつながる可能性があるからです。
成功への道筋は、まず事前準備として自社の目的、ターゲット、予算、納期、そして理想のイメージを明確に描くことから始まります。その上で、相見積もりを通じて複数の会社の実績や提案力、コミュニケーションの質、見積もりの妥当性を比較検討し、候補を絞り込みます。
そして最終選定の段階では、費用対効果を冷静に見極め、契約内容や修正ルールといった細部まで入念に確認することが不可欠です。
動画制作は、決して安価な投資ではありません。だからこそ、今回ご紹介したポイントを一つひとつ丁寧にチェックし、自社の目的達成に最も貢献してくれる、信頼できるパートナーを見つけましょう。
本記事を参考に、貴社にとって最適な動画制作会社を選び、プロジェクトを成功に導いてください。
もし、YouTubeに関する相談があれば、StockSun株式会社の鳥屋までお問い合わせください。
\完全無料のオンライン相談会を開催中/
YouTubeに関して相談する